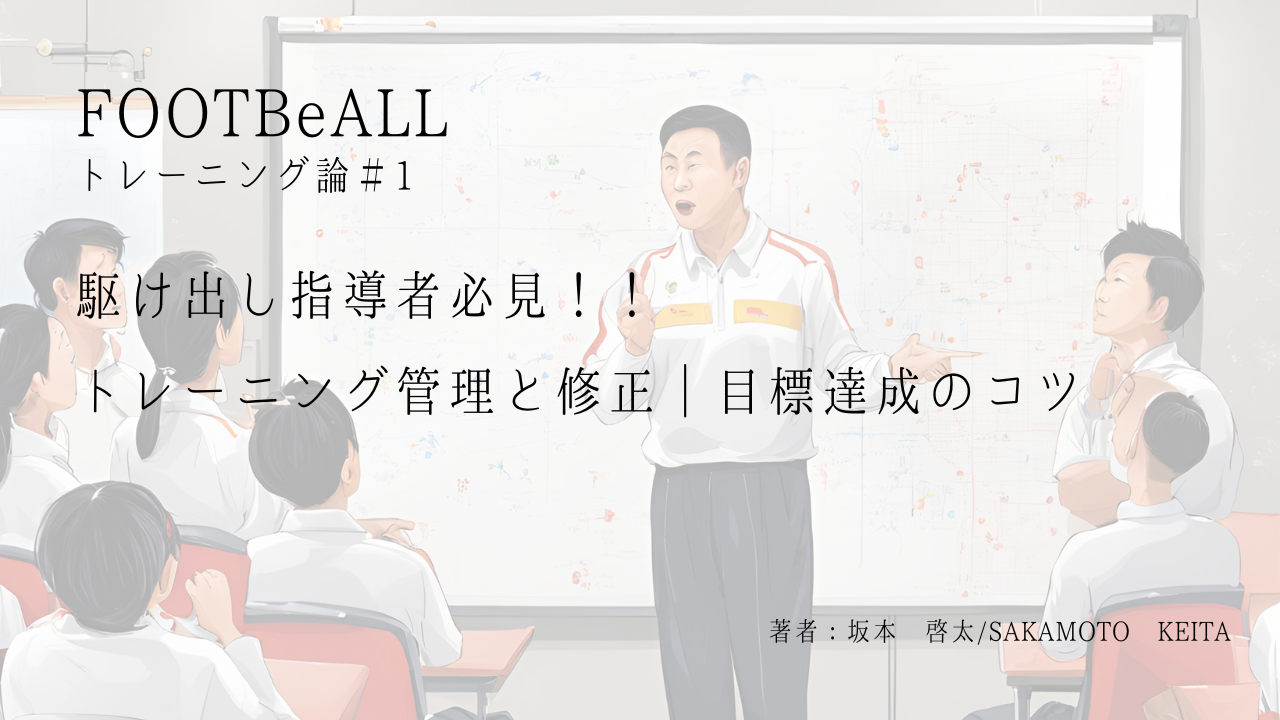得点力不足に悩んでいる・・・」
「フォワードが全然ボールを受けられない・・・」
そんなお悩みを抱えている指導者の皆さん必見です。
フットボールをきちんと理解することが選手たちの成長に繋がります。
この記事ではデスマルケの全てを解説しています。目の前の選手になんとしても成長してもらいたいという思いの指導者の方は是非最後まで拝読ください。
1. デスマルケとは
オフェンスにおけるオフザボールのアクションの1つで相手のマークを外してボールを受けるアクションをデスマルケと言います。

オフザボールのアクションとして、「サポート」がありますが、デスマルケとの違いを簡単に説明しておくと、サポートは味方やチームを助けるために行うもので、デスマルケは相手のマークを外して自分がボールを受けるために行うものです。

デスマルケを行った結果、味方やチームを助けることにつながることもあります。
2. デスマルケの起源
デスマルケとはスペイン語の"desmarque(マークを外す動き)"を起源としています。スペインからの輸入された言葉が指導者界隈ではだいぶ普及してきた感覚です。
3. デスマルケの重要性
フィジカルスタンダードの向上と組織化されていく攻守によって益々ボールホルダーに与えられる時間とスペースが少なくなる現代サッカー。ボールを持つ前から勝負は始まっていますし、ボールを持つ前には勝負は決まっているかもしれません。そんな時代の変化に伴い、オフザボールの質が求められていますね。
次に各シチュエーションでどのようにデスマルケが重要視されているか見ていきたいと思います。
(1) ビルドアップシチュエーション
ビルドアップとハイプレスの発展から自陣深くに引き込んだ状態からダイレクトな攻撃に転じる展開は多くなっています。だからこそロングボールを受けるためのデスマルケの重要性は高まってきています。
また守備も組織化が進み、コンパクトになり、役割が明確になり、さまざまなビルドアップに対する解決策を生み出され続けています。そんな中、集団的解決策ではなく個人としてマークを外しフリーになれる選手は貴重な選手です。
一見、デスマルケとはゴールを奪うために密接に関わるアクションだと思いがちですが、ビルドアップシチュエーションから重宝されています。
(2) チャンスメイク
先述したように守備の組織化は3ラインがコンパクトさ、ハイライン、さらにはゴールキーパーすらもスイーパー的な役割としてDFライン背後のケアを積極的に行うなど発展していっています。そんな中、一瞬の隙でラインブレイクできるかどうかもアタッカーとして求められる能力になってきています。
またトップレベルではテクノロジーの導入によりオフサイドの誤魔化しが効かない状態になっています。バルセロナはそれを活かし積極的なハイラインとオフサイドトラップを仕掛けています。
(3) フィニッシュ
現代、自陣ゴール前ではスペースは少なくなっており、そんな中で一瞬の隙を作るのはまさにデスマルケと言えるでしょう。実際、活躍するフォワードたちを観察すると卓越した身体能力やテクニックを持ち合わせていることは勿論ですが、地味なオフザボールの駆け引きがその高い能力を最大限活かせている秘密と言えるでしょう。
3. デスマルケの解説
(1) ボールホルダーがフリーな時、
ボールホルダーがフリーな時には「チームを前進させるため」「ゴールを奪うため」のデスマルケが必要になってきますね。ボールホルダーがフリーだとロングボールやサイドチェンジなど近く・遠く・左・右と多くのスペースが使えますし、ボールを失うリスクが低いです。なので、このタイミングで「チームが前進させるため」「ゴールを奪うため」にデスマルケを行い、攻撃に人数をかけることは効果的ですね。
さて、ではポジション別に見ていきましょう。
フォワードは基本的に相手DFラインの周辺でプレーする役割を持っています。DFラインの背後やDFラインとMFラインの間ですね。プレーするエリアが明確になったところで誰がどちらにプレーするのか迷いが生じてくると思います。その迷いを解決してくれる基準は「ボールの近くの選手からアクションを行う」ということです。基本的にボールを見てプレーしているという前提があるので、ボールの近くの選手はボールから遠くにいる選手を見ることは困難になります。一方、ボールの遠くにいる選手はボールを見た時に視野の中に自然とボールの近くにいる選手が見ることができます。そこでボールの近くにいる選手がDFラインの背後へアクションを起こした場合、ボールの遠くにいる選手はDFラインとMFラインのライン間でプレーすることができれば、相手DFはどちらかのスペースを与えることになってしまいますし、迷いを与えることができます。
ミッドフィルダー(ボランチ・アンカー)は基本的に相手MFラインの周辺でプレーする役割を持っています。相手DFラインと相手MFラインの間や、相手MFラインと相手FWラインの間ですね。基本的な考え方はフォワードと同じですね。
味方(ボールホルダー)に選択肢と、相手に迷いを与えながらプレーするためのデスマルケを絶えず行っていきましょう。
(2) ボールホルダーがピンチの時、
一方、ボールホルダーがピンチなら「ボールを保持するため」にデスマルケを行う必要があります。ボールホルダーが相手DFからプレッシャーをかけられており、使えるスペースにも限りがあります。相手DFのアプローチの向きにはプレーが難しいですし、プレッシャー下において精度の高いロングボールを蹴ることは難易度が高まります。そこで一旦、相手がプレッシャーをかけているエリアからボールを逃すための中継としてボールホルダーの近くでボールを受けることができればフリーな味方へボールを逃すことに繋がります。相手DFを制限をかけていることから当然マークを行い、簡単にボールを受けることを許してはくれません。
こちらもポジション別に見ていきましょう。
先述したようにポジションによってプレーエリアは大体決まっています。ただ注意したいのはボールホルダーがピンチの時にはボールに近いスペースしか使えなくなるという点です。なので、相手の背後を狙いにいってもかえって選択肢が無くなり、チームに悪影響を与える可能性があります。
そこで重要になるのが「幅」と「奥行き(深さ)」です。
スタートポジションで広く、深くポジションを取っておくことでピンチになった時に使えるスペースを確保できます。ボールを受けるために近付く選手は多くいますが、いつボールに寄るかが鍵になってきますね。
4. デスマルケのキーファクター
次に3つのデスマルケをどのように実践していけばいいのか、具体的な方法について解説していきたいと思います。
(1) ボールを保持するためのデスマルケ
・相手より先に動き出す。
・パスが出る前に動く。
・角度をつけて受ける。
(2) チームを前進させるためのデスマルケ
・ボールから横に離れながら動く。
・前が向けるスペースを確保しながら受ける。
・パスが出る前に動く。
・緩急をつける。
・守備の管轄の狭間を探る
・相手の背中に立つ。
・予備動作を入れる。
・緩急をつける。
止まった状態から急に動き始めたり、動いていた状態から急に止まる。
(3) ゴールを奪うためのデスマルケ
・ゴールポスト幅でプレーする。
・横に動いてボールから離れ、背中に潜り込んでから動き出す。
・タッチの寸前はボールに寄ることで相手より先に触る。
・DFラインより低い位置ならパスが出る前に動き出す。
・DFライン上ならパスが出る瞬間に動き出す。
・へそは侵入したいスペースに向けておく。
・視野の外から動き出す。
・守備の管轄の狭間を探る
・相手の背中に立つ。
・予備動作を入れる。
・緩急をつける。
止まった状態から急に動き始めたり、動いていた状態から急に止まる。
5. デスマルケのコンセプト
どの方法にも通づる大切な考え方と具体的な方法をご紹介していきます。
考え方を知ることが指導において最も大切だとも感じています。
・パスを受ける前にフリーな状態になっておくこと
・オフサイドに注意しながらプレーする。
・味方や相手がプレーする前に受け手主導でアクションを行う。
・スペースの前でプレーすること。
6. デスマルケの実践例
☑️ クリスティアーノ・ロナウド
☑️ ティモ・ヴェルナー
☑️ レヴァンドフスキ
☑️ エリング・ハーランド
☑️ ルイス・スアレス
- 関連記事 -
☑️ 個人戦術とは(近日公開予定)
☑️ 攻撃におけるオフザボールアクション 〜デスマルケとサポートの違い〜(近日公開予定)
☑️ 守備におけるオフザボールアクション(近日公開予定)
☑️ マークとは(近日公開予定)