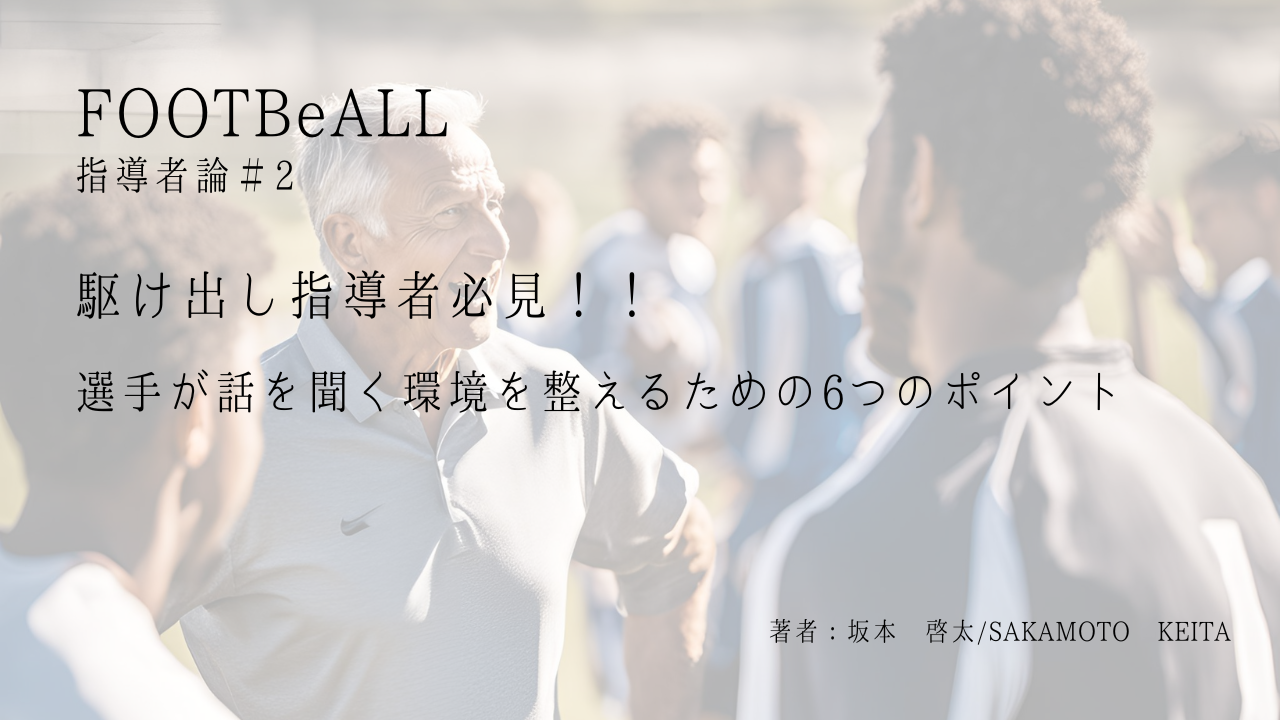最近、スペインサッカーの情報が増え、聞き慣れない“デスマルケ”という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
今回は得点するためのオフザボールで重要な個人戦術アクション「デスマルケ」について実際の選手がどのように行なっているかをみていきたいと思います。
今回ピックアップしたのはプレミアリーグのトッテナム所属のドイツ代表:ティモ・ヴェルナー選手です。
得点をする上で最も大きな障壁となるのはやはり相手ディフェンダーです。ゴール前となれば執拗にマークも厳しくなります。上手い選手であれば尚更。トップレベルの選手たちはどのようにして得点するためのスペースを生み出しているのでしょうか。
✅ 動き出す瞬間からフリーになっておく
マークに捕まった状態から振り払うような印象が強いデスマルケ(マークを外す動き)ですが、そもそもマークに捕まらない工夫を多くしている印象を受けました。その方法を2つ紹介したいと思います。

☑️ 相手の背中から動き出す

・相手からマークされた時に有効。
日本で多いマンマークの守備。それに対する解決策を持っているだけで大きな影響を与えます。味方もボールのみを見てしまい、強烈なマークを受けてしまうことがとても多いです。
・相手は基本的にボールを監視するので、フリーになりやすい。
守備の原則を理解することが大切です。相手は基本的にボールを監視するので、背中側でプレーすることが必然的にマークを外すことに繋がります。それでも視野内でプレーしようとすれば大きなスペースが生じるので守備側は対応に困ることになります。
☑️ 中間ポジションから動き出す
・ゾーンディフェンスの相手に有効。
曖昧なポジショニングを取ることでマークがはっきりせず、誰がついていくか混乱させることでフリーになりやすいです。
・絶妙なポジショニング調整。
中間ポジションにただ立つだけではマークについてこられたり、マークを受け渡されたりして対応されてしまいます。なので、ついてこられる間は動き続け、マークを受け渡されそうになると止まる。そうやって守備の管轄の狭間を見つけることが求められます。
【最後に】
日本の少年サッカーではオンザボールの基本を練習するチームは多く見かけますね。対面になって浮いたボールをインサイドやインステップ、ヘディングで扱うものです。
しかし、オフザボールの基本のレベルもどんどん上げていっているのが日本のトップレベルの現状です。地域の街クラブや少年団でもオフザボールの基本をレベルアップさせていかなれかば差がますます広がるでしょう。
チーム戦術が発達していく中でやはり重要になるのが「個人」だと実感しています。どんなにいい設計図を描けてもパーツが腐っていたり、錆びていたり、亀裂が入っていればそこからたちまち破損してしまいます。
フィジカルが成熟していない小学生の間は技術や戦術を磨き、個人としてできることを増やしていくことがサッカー選手としての土台になります。
今回紹介した内容はミッドフィルダーのボランチやアンカーの選手も活用できます。

引用元:Timo Werner - Desmarques / Matías Ezequiel Navarro García