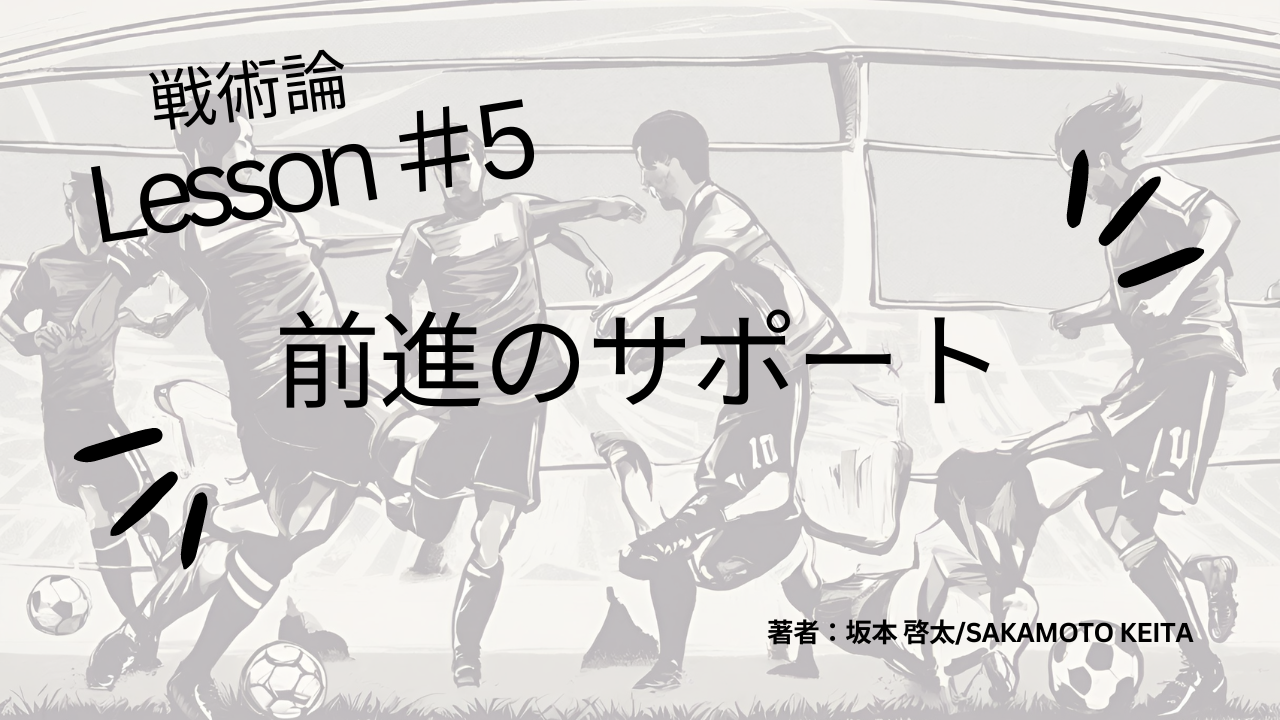メディアなどで
「ドイツサッカーはこうだ!」
といった記事を目にすることがあります。しかしそれらのなかに「本当にそうかな?」と首をかしげたくなるものもあるのが現状です。今回はそんな一例を出して見たいと思います。
ドイツでは小学校低学年までは審判なしで試合が行われることがあります。
『フェアプレールール』と呼ばれているスローガンの下に成り立っており「ファールやスローインの判断を選手自身に任せ自主性を高める」ことを目標にしています。一見素晴らしい考え方ではりますが、実情ははっきり言って全く違い大きく分けて3つの問題があります。
まず大きな問題は審判の数です。基本的にドイツでは日本のようにコーチが笛を吹くことはありません。協会から審判が派遣されるのです。その審判の数が試合数に対し少ないという現状があります。
また経費の削減という観点も挙げられるでしょう。ドイツでは審判に対し主催者チーム(ホームチーム)は謝礼を支払います。子供の試合であれば20€位が相場だと思います。そのお金を節約するために低学年では審判を採用していないのです。
運営面の観点からも問題は浮上しています。「ファールやスローインの判断を選手自身に任せ自主性を高める」ことを目標にしていますが実際は判定を巡り意見が食い違うことが多々あり揉めることも珍しくありません。場合によっては判定を巡り試合が中止になるケースもあるほどです。
もちろんこの『フェアプレールール』を通じて選手たちの自主性が高まっている側面もあるでしょう。しかしプレーしている子供たちは勝つために『良い意味でズルをする』こともあるし、勝つことを主眼に置いている監督が必ずしもこのルールを守っているとは思えません。つまり日本のメディアで紹介されているような素晴らしいことばかりではないのです。
今後もこのコラムを通じてドイツの良いところも悪い面も現状をそのままお伝えしていこうと思っています。
SUGIZAKI