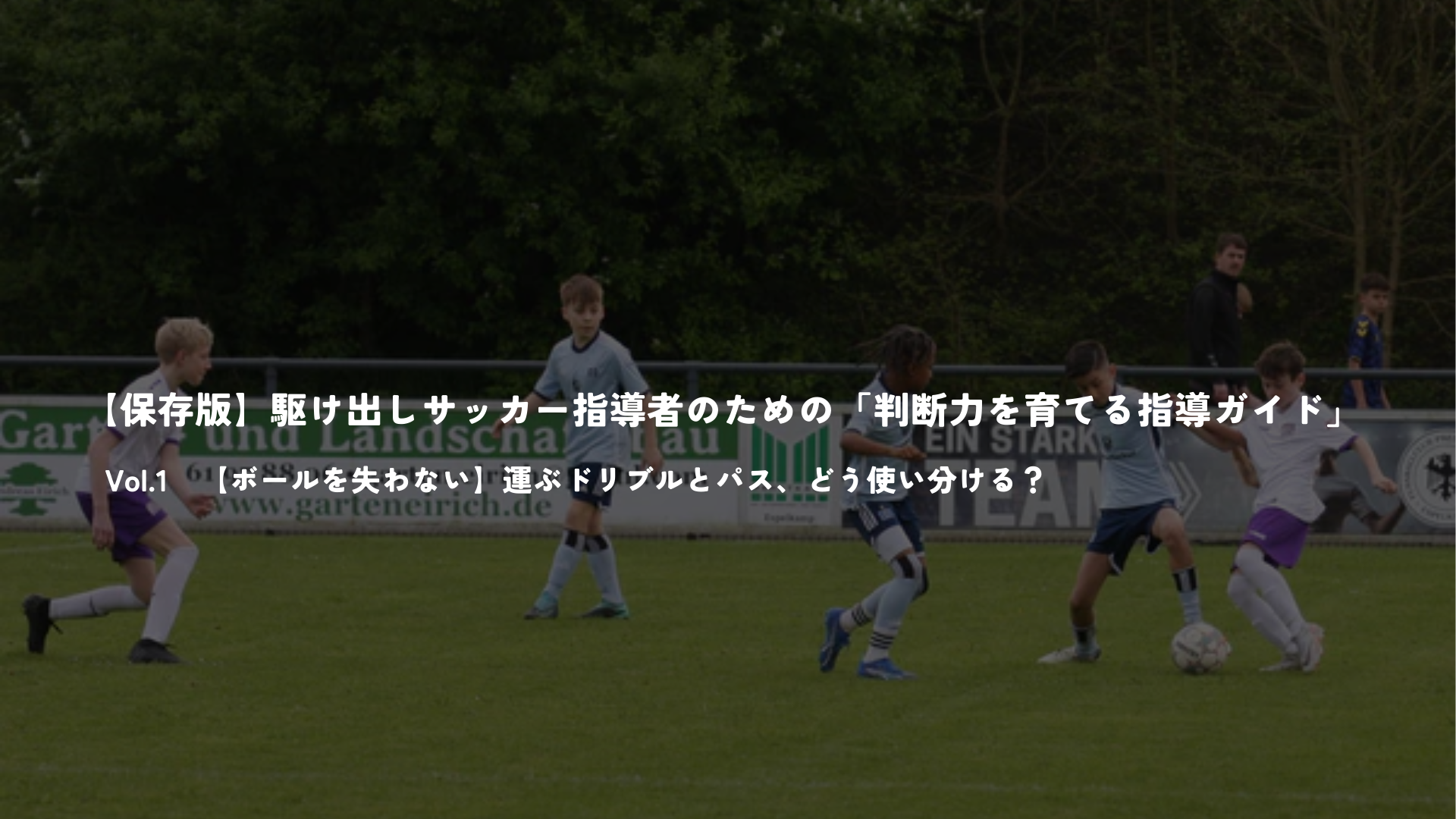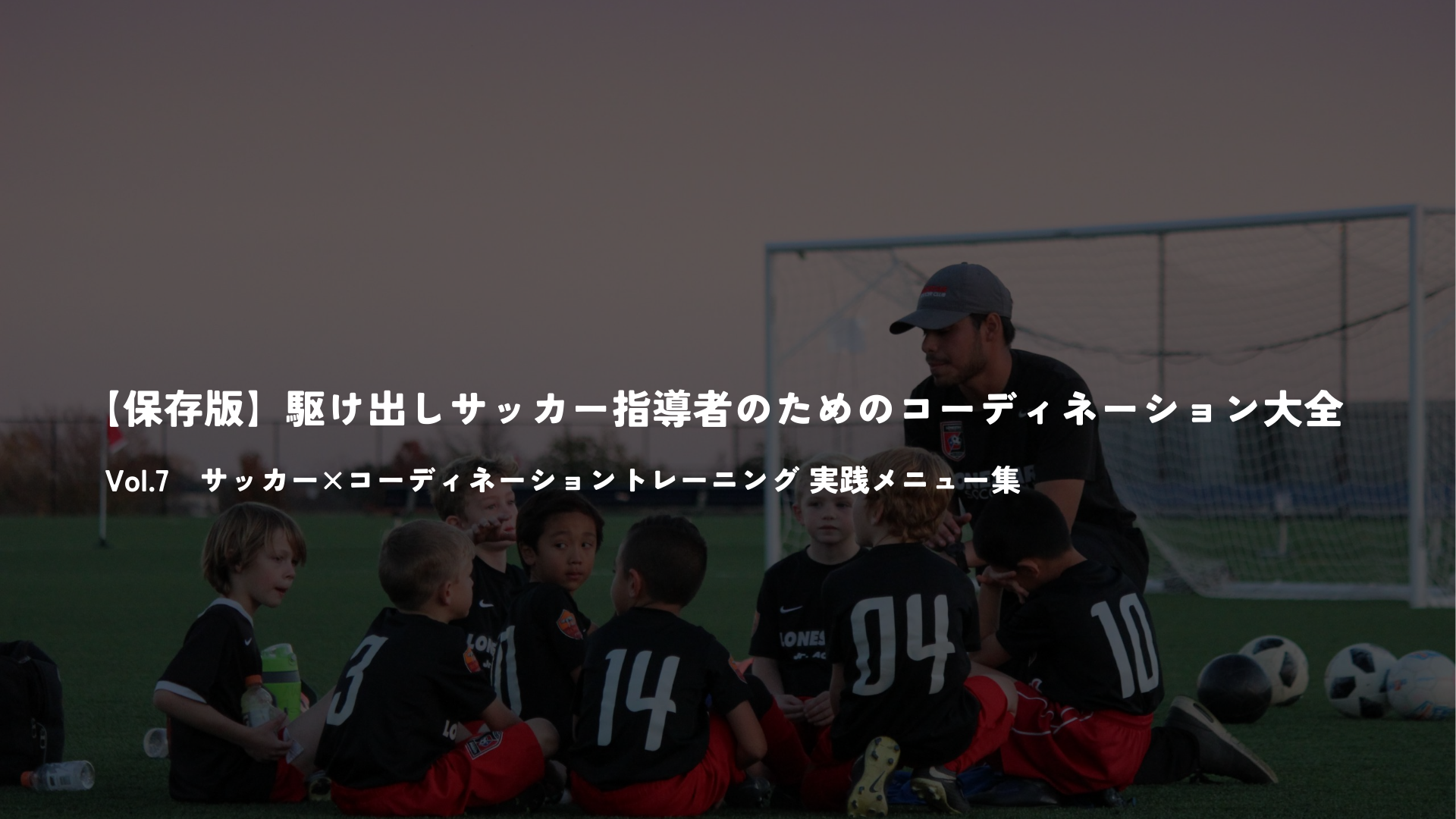Vol.1TR(トレーニング)って何?〜“練習”との違いとは〜
✓こんな人におすすめ!
-
「トレーニング」と「練習」の違いがよくわからない
-
指導ライセンス講習で聞いた「TR理論」がしっくりきていない
-
サッカーの練習を“ただの繰り返し”にしてしまっている気がする
-
スペインやヨーロッパの指導スタイルに興味がある
✓このシリーズを読むことで得られるもの
-
トレーニングの本質がわかる
-
メニューの“設計力”が身につく
-
選手の「自発性」を引き出す指導に近づける
-
サッカーの原理原則とリンクした指導ができる
-
指導の“引き出し”が増える
✓読み終えた頃には…
-
指導に「明確な意図と設計」が宿るようになる
-
トレーニングメニューに意味と流れが生まれる
-
選手の変化・成長に気づきやすくなり、指導が“楽しく”なる
「毎日一生懸命練習しているのに、なぜかうまくならない選手がいる」
「同じメニューをやっているのに、効果が出る選手とそうでない選手がいる」
そんな経験はありませんか?
もしかすると、その原因は「練習」と「トレーニング」の違いを理解せずに、“ただ繰り返す”ことが目的になっているからかもしれません。
この章では、JFAの指導者ライセンスやスペインのコーチ養成機関で学ぶ「TR理論」の基礎として、そもそも「トレーニングとは何か?」という問いから出発します。
Topic1「TR(トレーニング)」とは?
サッカーの指導現場でよく使われる「TR(トレーニング)」という言葉。
一見、「練習」と同じように聞こえるかもしれませんが、実は明確な違いがあります。
日本サッカー協会(JFA)やスペインの指導者養成機関では、TRを以下のように捉えています:
「目的を持った計画的な学習プロセス」
つまり、TRとはただ身体を動かすだけの「繰り返し」ではなく、選手が自ら気づき、理解し、変化・成長していく過程そのものを意味します。
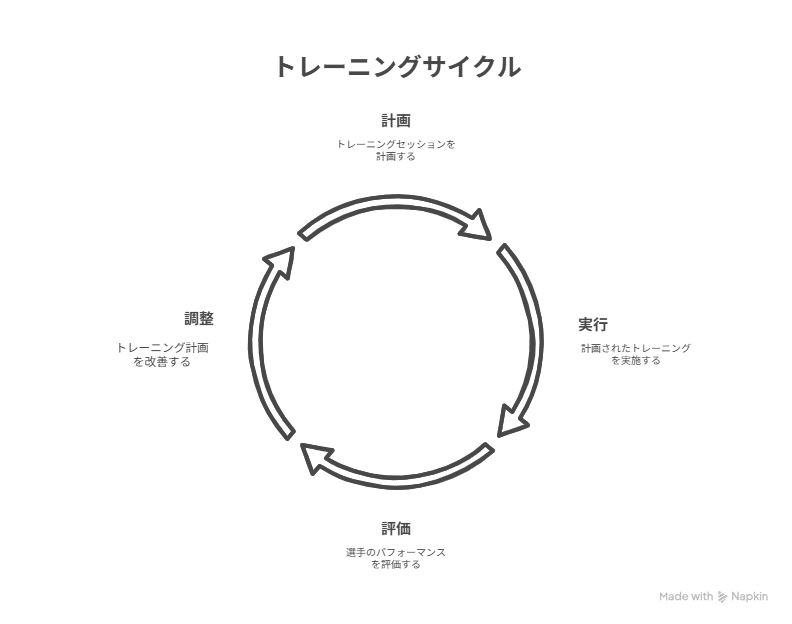
Topic2「練習」との違いとは?
▶ 練習(Practice):
-
技術の反復・習熟が中心
-
コーチ主導の指示型
-
一方向的
-
成果が「できる・できない」で評価されがち
▶ トレーニング(Training):
-
課題の発見・解決が目的
-
選手の“自発的学習”が中心
-
相互的・多角的
-
プロセスと気づきの連続で評価される
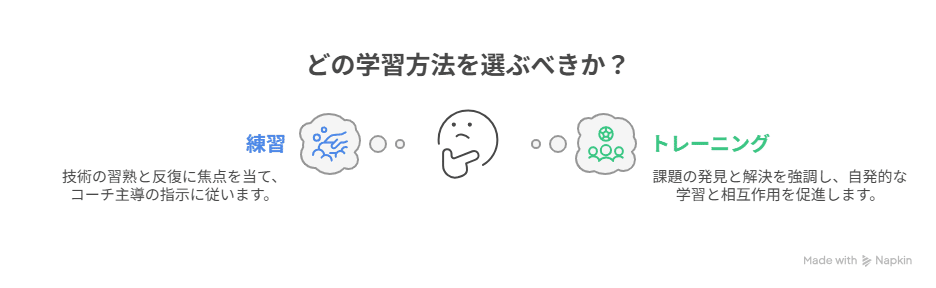
Topic3 TR理論の基本的な考え方(JFA × スペイン)
▶ JFAの考え方:
-
「トレーニング」は“ゲームからの逆算”
-
TRの目的は、試合の中でプレーを向上させること
-
年代・レベルに応じて、徐々に複雑な状況設定にしていく
▶ スペインの考え方:
-
「選手は自ら学ぶ存在」
-
コーチは“学びの場”を設計するファシリテーター
-
TRは、判断(decisión)を鍛える場
どちらも共通しているのは、
「トレーニングとは、“試合に生きる判断と実行”を鍛える行為である」
という点です。
Topic4 指導者にとっての気づき
TRの本質は「選手に変化をもたらすこと」。そのためには、以下のような視点が欠かせません。
-
トレーニングの目的を明確に持つ
-
選手の自発的な気づきを引き出す
-
単なる“ドリル”で終わらせず、“ゲーム”とのつながりを意識する
Topic5 この章のまとめ
-
「練習」と「トレーニング」の違いが明確になる
-
サッカー指導におけるTRの目的と意味を理解できる
-
日本とスペインのTR理論に共通する本質を知ることで、自分の指導を見直すヒントが得られる
✓次回予告
【第2章】「アナリティックって何?」〜技術を分解して理解する〜
👉 技術習得の“第一歩”となるアナリティックTRの正体に迫ります!