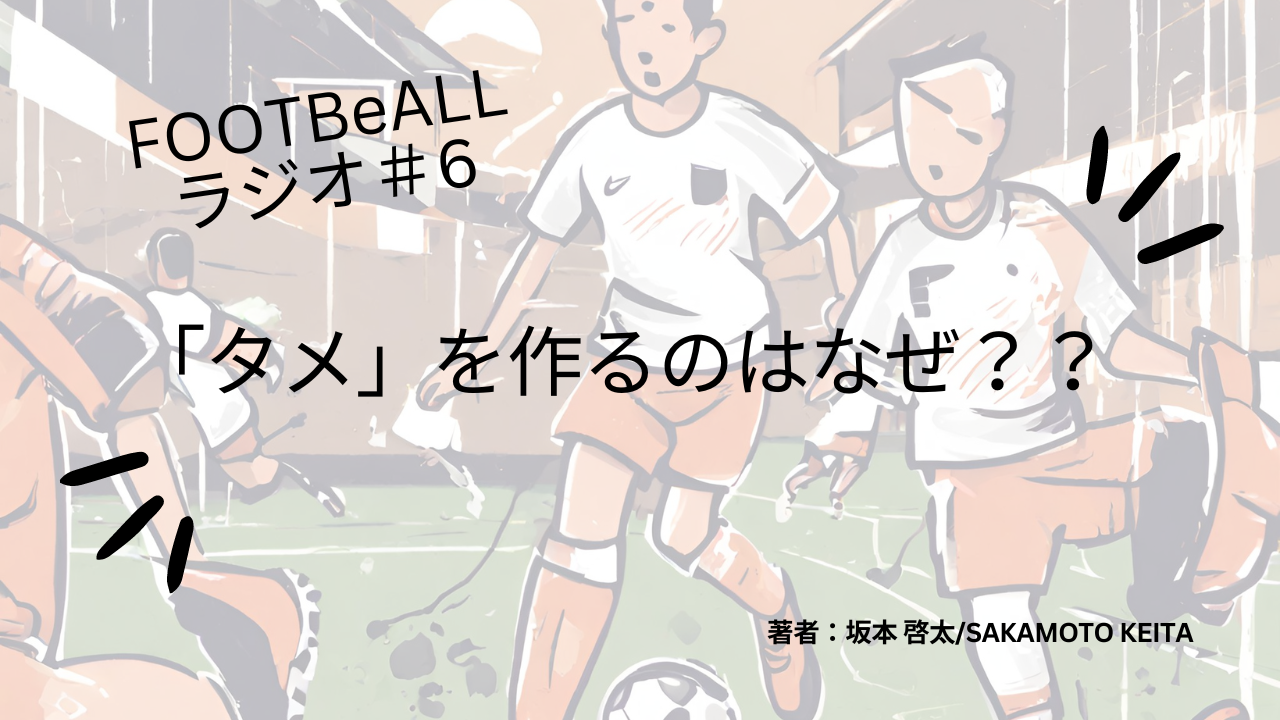選手が活き活き輝くチームにしたい...。
そんなお悩みを解決します!
✅ JFA公認B級コーチライセンス、公認メンタルコーチングライセンスを取得、幼児から中学生まで幅広く指導しているコーチが記事を書いています🔥
有料会員の3つの特権
✅ あなたの悩みが解決する記事を「圧倒的な低価格」でご提供!
✅ 公式LINEを用いた相談が可能になり、専門家が完全個別対応!
✅ 1記事の価格で、全記事が読み放題。今後も記事をどんどん更新!
あなたの夢に必要なものを、プロフェッショナルと共に
✅ サッカーコーチは勿論、教諭や理学療法士、アスレティックトレーナー、鍼灸・あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、登録販売者、レントゲン技師、スポーツ栄養士、管理栄養士、メンタルコーチなど各分野のプロフェッショナルが在籍。
フットボールの理解と併せて、あなたの夢をプロフェッショナルがアシストします!
WE GO - 一緒に行こう、夢へ -
▼たった "¥198"で記事の全編をチェックする▼
記事の全編では、試合中や練習中における選手との
コミュニケーションについて解説しています
🔥期間限定で有料記事を公開中
選手の理解度に応じた個別対応とアクティブラーニング
選手一人一人違って、同じ人はいません。だからこそ、一人一人に最適な関わり方があります。だからこそ個別対応性が必要となってきます。
またサッカーという競技特性の側面や現代日本におけるサッカーの位置付け、時代の移り変わりから「アクティブラーニング」が重要になってきています。
ここでは個別対応性とアクティブラーニングの具体的な方法について解説していきます。
(1) オーガナイズを工夫する
選手の理解度を「守・破・離」で分類した場合、「離」に該当する選手に対して比較的有効なアプローチです。
理解度の高い選手には彼らが育つ環境だけ整えてあげることが最も重要です。

ハイプレスを行うことで、①カウンターができる(得点できる)オーガナイズ設定、②相手のミスを誘い、自チームボールからのリスタートになったらコーチからの配給でカウンターができるルール設定、等で選手たちにどんなメリットを与えるかと獲得させたいテーマを結びつけることで選手たちが自発的に考え、能動的にプレーすることに繋がります。
(2) コーチングを用いる
選手の理解度を「守・破・離」で分類した場合、「破」に該当する選手に対して比較的有効なアプローチです。
ある程度、答えを自分たちで導き出せる理解度にあることから直接的な答えを提示せずともヒントを与えることで選手が自発的に答えに気付き、能動的にプレーすることに繋がります。
COCHING POINTS
✅双方向性
ティーチングとの大きな違いは選手の中で答えがあり、それらを導くのがコーチングであるということです。
プレーにおける目的達成のためにどんな手法を使えばいいのか、をコミュニケーション取ったり、選手のアクションを観察する時間や選手が考えていることを聞く時間が双方向性をもたらします。
✅質問の使い分け
主にオープンクエスチョンとクローズクエスチョンがあります。
オープンクエスチョンは「〜どうしたらいい?」など広がりのある質問になります。使う際にはサッカーの目的や原理に帰ることがポイントになります。
例)どうしたら得点できるかな?、ゴールはどこについているかな?どうしたらボールを奪うことができるかな?等。
選手の反応や理解度を考慮しながら質問の抽象度をコントロールしたり、クローズクエスチョンに切り替えたりしてみましょう。
クローズクエスチョンは「YES or NO」「A or B」など選択肢が与えられている質問になります。選手の理解度が高くない場合や事実確認の場合、意思の再確認の場合に使うことで効果を発揮します。使い過ぎると誘導尋問のようになってしまい、能動性が失われるため注意が必要です。
✅継続性
一度伝えたことでもプレーする中で意識が薄まることは多くあります。
基本的に人間は一度のことしか意識できません。意識できていると感じるのは高速に意識を切り替えているということになります。
だからこそ、継続的にコーチングすることで意識を取り戻すサポートが必要です。
思考習慣の改善には〜6ヶ月程度かかるという科学的な発見もあります。
(3) ティーチングを用いる
選手の理解度を「守・破・離」で分類した場合、「守」に該当する選手に対して比較的有効なアプローチです。理解度が浅く、自分で答えを導き出すのは困難であるフェーズにおいて気付きを待つのは時間がかかることかもしれません。成功体験を積むことで競技への興味・関心が高まる場合もありますし、選手の中で答えが明確になるからこそ思い切ってプレーできることにも繋がります。
右か左か直進か分からない交差点にいると想像してください。きっとスピードが落ちるはずです。時には道を示すことも大切なことです。
TEACHING POINTS
✅ニーズを作る
我々はそもそも選手がうまくなるために存在しています。
選手が悩んでいるものに対して適切な助言を行い、選手の成長を促す形があるべき姿です。困っていないのに助言をされても「おせっかい」に感じてしまいます。だからこそ、強豪との練習試合や難しい練習内容、オーガナイズ設定で選手が困るシチュエーションを作り出しておくことは大切なことです。
コーチが伝えたいこと=選手が求めているもの → Win-Winの関係を構築することで効果的にティーチングを行えます。
✅信頼獲得
人は「何を言われるか」より「誰に言われるか」が重要な生き物です。ティーチングした内容どうこうではなく、信頼できるコーチの助言を聞いてみようというように信頼を獲得する必要があります。
信頼を獲得するためには練習前の何気ない日常会話や選手の考えに理解を示し、批判しないことが大切です。
✅ベネフィット
コーチが伝えたい答えがなぜ有効なのか、選手にとってどんなメリットがあるかを理解し、説明することで選手の納得感も高まります。
Ex.) 【伝えたいこと】フリーで前進しよう】/【選手のメリット】フリーで前進すると良い状態でシュートに入れるよね
✅明瞭な提示
5W1Hを意識した明瞭且つ簡潔な説明やデモンストレーションを行うことで選手に取っては理解しやすいものになります。
基準を提示する際には一度みんなを集めて行うことで効率よく伝えることができるかもしれません。
✅フィードバック
伝えた内容に挑戦する選手に対して積極的にフィードバックすることで選手のモチベーションは高まり、行動の再現性も高まります。「褒める」というより「認める」という感覚が適切です。
選手の挑戦自体を「ナイスチャレンジ!」で拾い、選手のアクションを「もう少し早いタイミングで!」とジャッジし、選手の成功を「そのタイミング!ナイスプレー!」と見逃さないことで選手が積極的に挑戦するようになります。
なぜ、個別対応とアクティブラーニングが必要なのか
原因が違うと、対処法も異なる
腹痛への対処も原因が「食中毒」なのか「便秘」なのか「ストレス」なのかで今後の対策が変わっていくように、選手一人一人の理解度や価値感、身体構造によって「何を伝えるか」が変わります。だからこそ一人一人をよく観察して個別対応を行う必要があります。
サッカーと能動性の親和性
サッカーにおいて選手の能動性は重要な要素です。ピッチの中はVUCA(Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)という4つの言葉の頭文字をとった造語)に該当します。それはつまり同じシチュエーションは二度と来ないことをし、コーチに与えられた答えは別のシチュエーションでは効果を成さないことを意味します。だからこそ選手自らが素早い決断を次々に迫られる中でプレーできるために能動性を獲得する必要があります。
アクティブラーニングの効果
コーチングやオーガナイズの中で獲得していくスキルは「自ら体験する」に該当し、平均学習定着率が75%と言われています。
それは選手として効率的にサッカーを学び、競技力の向上に繋がります。
現代日本とサッカー
現代においてサッカーは楽しくなくてはならないものに変化してきていると思います。特に普及 / 育成段階において「楽しいもの」=選手自身にメリットがあるもの、でなければならず、それは娯楽が発達している日本において、多くの誘惑が常に存在しているからです。
選手が能動性を発揮し、「楽しいもの」であると感じることで娯楽が発達している日本においてもサッカーを選択してくれる重要な要素だと感じています。
\無料相談受付中/
公式LINEでは現場で挑戦する指導者へお悩み相談を受け付けております!
唯一無二の現場であるからこそ、個別対応性が必要になってきます。