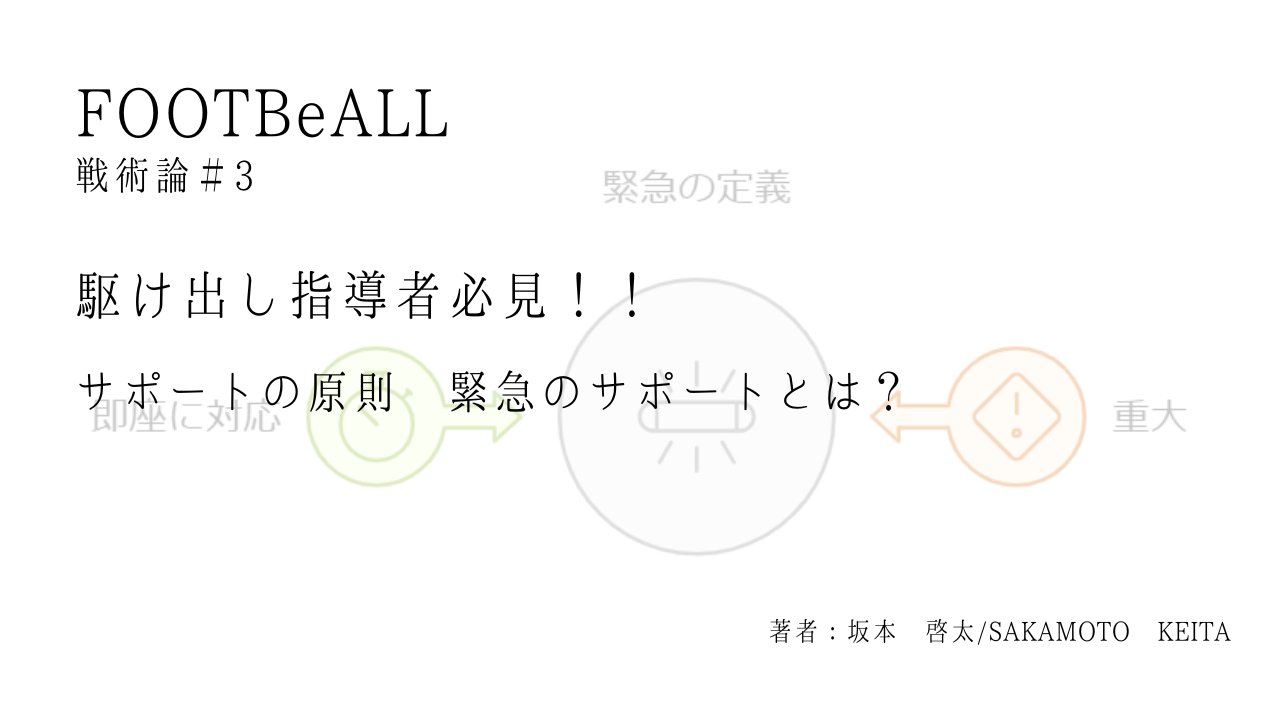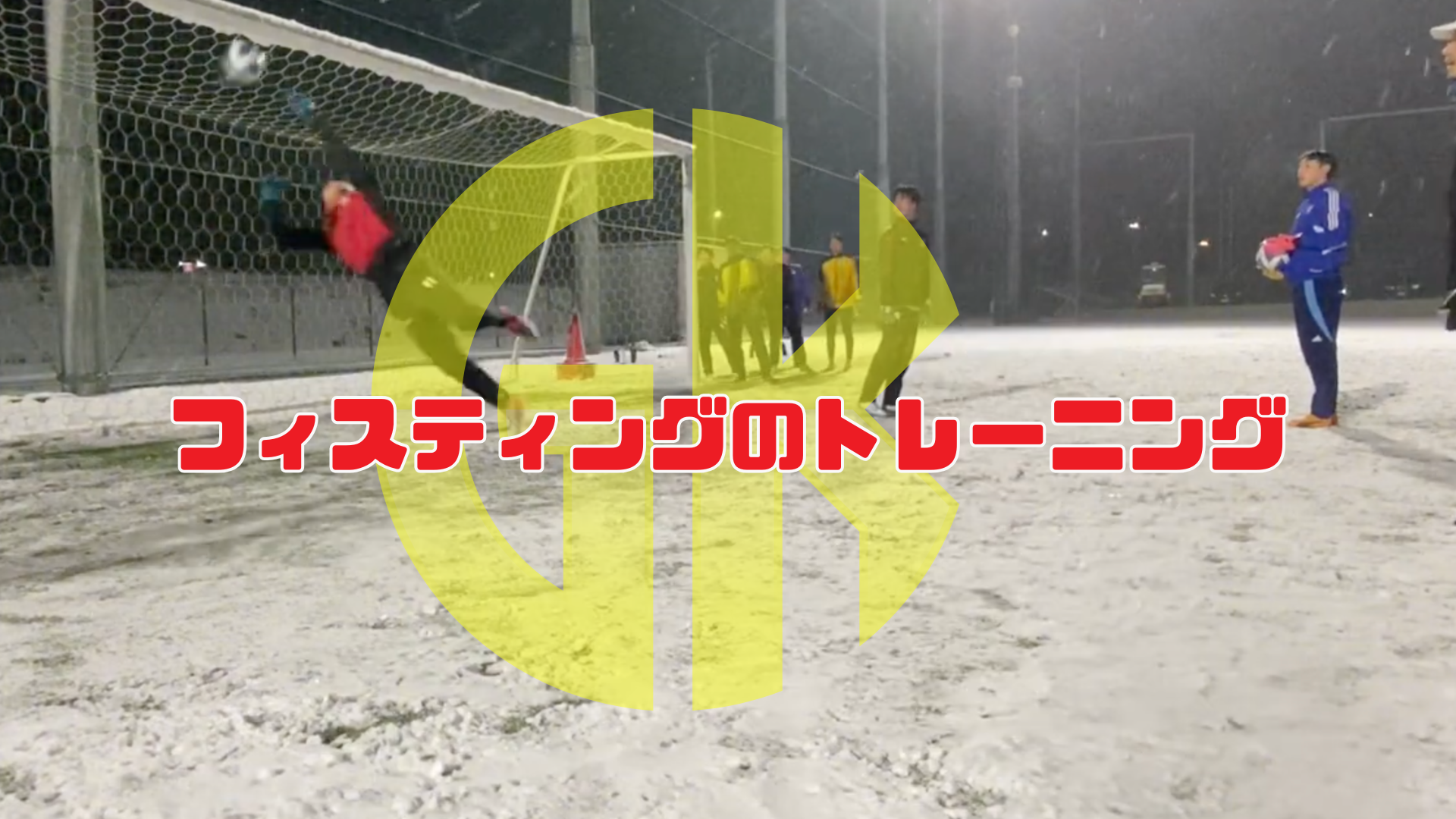練習メニューの解説
5対5+サーバー+GK
形式:オレアーダ(ワンウェイ)
人数:12名
年代:小学生高学年
ルール:
・サーバーからの配給でトレーニングを開始します。サーバーはコーチでも問題ありません。
・攻撃側がゴールを決めたら、また攻撃側からの再開とします。
・守備側がボールを奪ったらサーバーへのパスゴールもしくはサーバー横をドリブル突破とします。
・すぐリスタートできる場合はスローイン再開。
・ゴールキック・コーナーキックは無しでサーバー配給スタート。
・守備側がボールを奪ってビルドアップを成功とした場合もしくは時間で攻守交代。
・最終的に得点数が多い方が勝利。
オーガナイズポイント
ゲームからの引き算
我々のチームで直近で1−2−4−1のフォーメーションを採用していたのでこのような選手の配置になっています。自分たちのGKとCBを1人減らした形ですね。
対象のシチュエーションを多くプレーすることがトレーニング構築で大切なポイントの1つですので、自陣ゴール(=カウンター)を除いています。

獲得させたい要素から逆算
狭いスペースでの突破を獲得させたいのであれば2トップスタートにすることも問題ありません。獲得させたい要素がどのよう なオーガナイズなら必要となるか?を理解しておく必要があります。
相手の守備が3バック&2ボランチなのか、4バック&1ボランチなのかで攻略に必要な要素が変化し、それらが選手にとってトレーニングになります。
ルール設定
上記同様、ZONE3の攻撃にフォーカスしたいのでサッカールールではなくコーナーキックやゴールキックを除きました。
指導者が獲得させたい要素と選手が望みが合致することが大切だと考えています。この練習の場合であれば、「守備側がボールを奪ってビルドアップを成功とした場合に攻守交代」が該当し、このルールにより守備を行うこと、攻撃がボールロスト後のカウンタープレスをアクティブに行うことが予想されます。
トレーニングの狙い
得点力不足を分解すると、「ゴール期待値」と「チャンス回数」を高めていくことで問題を解消できると考えます。
ゴール期待値を高める
ゴール期待値というと難しく聞こえますが、簡単に言うと「確率の高いシュートを打つ」ということです。ハーフラインから打つシュートとPKでは後者の方が確率が高いと言えます。基本的にゴールとの距離と角度で決まると言えます。そこで重要なエリアとなるのがDエリアです。ビエルサラインとも言われるかもしれません。このエリアにボールと人を送り込むことができればゴールの可能性は高まります。
チャンス回数を増やす
そのままで50%のシュートを4回打てば、理論上2点入りますし、50%のシュートを1回しか打てなければ1点入るか入らないか、ということになります。チャンス回数を高めるには「再現性を持って攻撃すること」「二次攻撃・三次攻撃に繋げること」が重要になります。詳しく解説していきます。
「再現性を持って攻撃すること」
再現性とは、何度も同じような形で現象を起こせることを指します。なので、チームとして同じような形で危険なエリアへ侵入することを可能とすることが必要になります。これはサッカーの原理原則を理解することや質的優位を活用することで可能になります。
同じシーンは2度と来ないとされているサッカーですが、抽象化するとそんなことはありません。この抽象化が再現性には大切な考え方です。
指導者として「原理原則を理解する」ことで再現性を高められるようになりたいですね。
そしてここで大切になる原理原則が【原理:相手守備者が存在する】ことから【原則:スペースから前進すること】や【原則:フリーから前進すること】が挙げられます。
いかに危険なエリアに入る前に相手のフォーメーションや守備の方法から再現性を持ってスペースやフリーを見つけ出すことをトレーニングする必要があります。
「二次攻撃・三次攻撃に繋げること」
これは自分たちの攻撃を終えて、相手ボールになったボールをいかに高い位置で、いかに素早く奪い返せるかを指しています。
有名な著書・スラムダンクで山王戦にて安西先生が桜木にリバウンドの重要さを説いたシーンがまさにそれです。


どう得点を奪うか?というクロスやフォワードへの言及は多いですが、跳ね返されたボールをどう回収するか?という視点は指導者を1つレベルアップさせるでしょう。
そのための逆サイドやミッドフィルダー、ディフェンダーのポジショニングが肝になります。
トレーニングできるコンテンツ
トレーニングしたいコンテンツを頻出させるためのメニュー構築が指導者としての腕を見せ所ですね。攻撃側のフォーメーション、守備側のフォーメーション、噛み合わせ、ディフェンスラインの高さの初期設定などがキーポイントになりそうですね。
オンザボールアクション
シュート、クロス、突破のドリブル、スルーパス他
オフザボールアクション
3人目のサポート、前進のサポート、背後へのランニング、マークを外す動き(デスマルケ)
得点力不足を解消するキーポイント
エリア内へ侵入する前に
効果的にエリア内へ侵入し、得点力不足を解消するためのポイントは「ライン間に侵入すること」にあると考えています。それは「スルーパスが通りやすくなる」「ディフェンスラインが食いつく」という2つの理由からです。
「スルーパスが通りやすくなる」
ディフェンスラインとの距離が近くなり、破るラインが1つだけになるのでスルーパスが通りやすくなります。グラウンダーのスルーパスも通りやすくなるのでピッチとの摩擦でボールが残りやすくもなります。そういったことからライン間への侵入が効果的な1つの理由です。
「ディフェンスラインが食いつく」
前を向かせてしまうとスルーパスの大ピンチを迎えることから相手ディフェンスをアラートになり、アプローチを行います。ディフェンスラインが動くことで背後のスペースがより大きくなったり、サイドチェンジへの対応も困難になってきます。相手ディフェンスを上下左右に揺さぶり続けることが得点の大きなチャンスを作り出すことになります。
紹介メニューで解説
上記の通り、ライン間への侵入を試みた際に障壁となるのが相手ミッドフィルダーです。そう考えた時の解決策をいくつか紹介したいと思います。
ワイドレーンから攻める
相手は2ボランチなので、シンプルに手薄なワードレーンから攻めることです。この際にワイドアタッカーは高さを調整しながら(=少し落ちながら)前向きを保ちながらプレーすることが鍵になります。
相手としては「①ワイドアタッカーへのマークを厳しくする」「②ミッドフィルダーがスライドする」で対応してくることが予想されます。これらに対する解決策も用意しておく必要がありますね。考えてみてください。
サイドチェンジを使う
「②ミッドフィルダーがスライドする」に対する1つの解決策だと考えます。こうすることでまた手薄なワイドレーンから攻められますね。サイドチェンジの際に外回りではなく、ブロックの内側を経由してサイドチェンジすることができるとワイドレーンにより大きなスペースを与えることができます。
ポジションを変える
スタートポジションのままだとマークがはっきりして、ズレが生まれづらい状態です。なので、CFがミッドフィルダーの間にやや落ちながら3対2の数的優位を作り出します。それによって、相手は迷いやズレが生じ、フリーになった瞬間にライン間へ侵入できます。