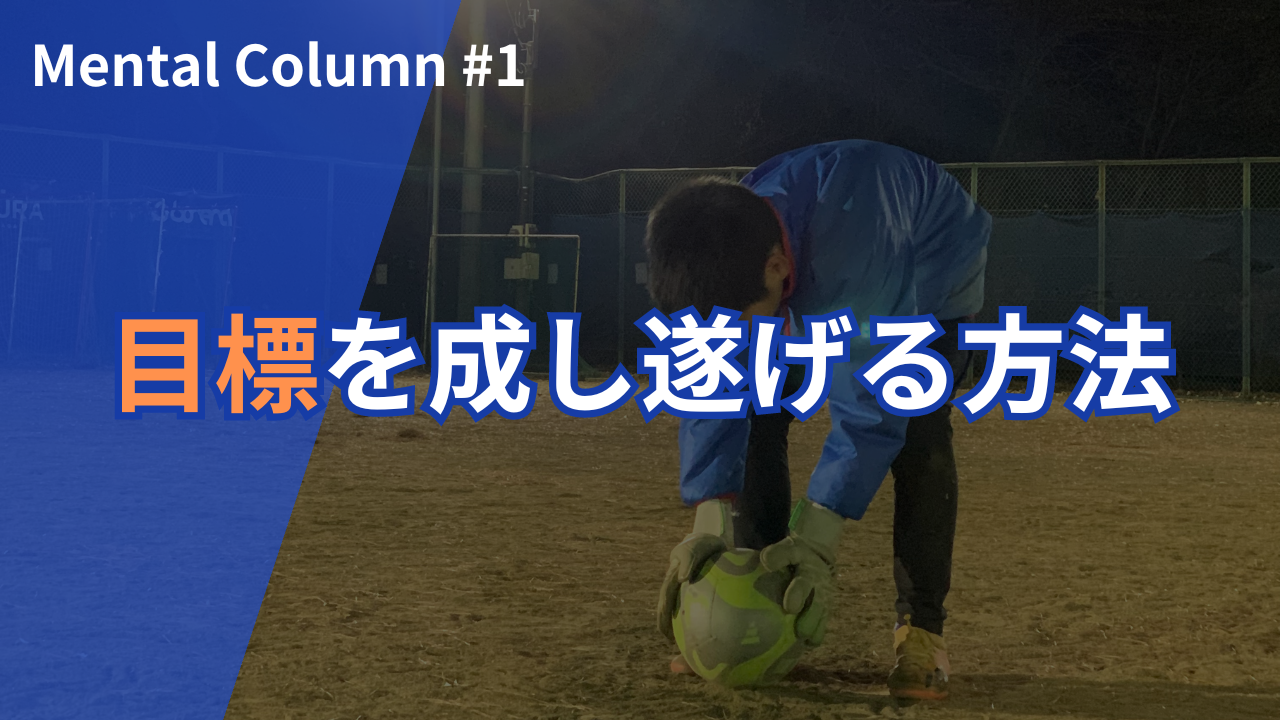GKコーチがいないチームの指導者たちへ伝えたいこと
(日本のGKを強化するために我々ができること)
ジュニア年代、ジュニアユース年代においてGKコーチがしっかりと付いているチームはかなり少数派に感じている。ユース年代でも私立ではいるが、公立ではなかなかコーチを見つけることができない。それだけ日本はGKコーチの数が不足していてGKにおける適切な指導や関わり方が不十分なのが現状だ。
さらに日本人の気質として、協調性を重んじる反面、自分だけが異質な役割、責任を負われるGKは今も好んでやりたがる子どもたちは、そこまで多くはない。そして、試合中ともなれば、こんな声がベンチから飛び交う。「キーパー取れよ!!」「出ろよキーパー!!」「なんで声かけないんだよ!」「蹴るな!」
私はベンチで叫ぶ彼らに問いたい。
「適切な指導をできた中で言っているのですよね?」
つまりどういうことかというと、
なぜそのエラーが起きたのかわかってますか?
いつ、どんな準備が必要だったかわかりますか?
プレーにおけるアクション自体のポイントは理解してますか?
普段どのように反復し、不安要素を取り除き挑みましたか?
ということを問いたい。
1つここで例を挙げるとすると、
サイドから相手のアタッカーがドリブルでペナルティエリアに侵入しマイナスにグランダーでパスを出す。中のFWがダイレクトでシュートを放つ。そのシュートがGKの正面で顔の脇に飛んできた。GKがキャッチングを試みたがファンブルしてしまい、そのまま両手を抜けてゴールインしたとしよう。
ここでベンチから見えた視点はどうだろう。
恐らく、撃たれたシュートにGKがファンブルした「現象」のみを観てしまわないだろうか。そうすると恐らくベンチのフラストレーションはGKのキャッチン、グのエラーに矛先がいく。たまたまシュートが顔の近くだったから尚更だ。
「何してんだよ!それ取れなくて何とれるんだGK!!」
では、このシーンをどのように考えるか解説したいので、指導者は理解してほしい。
まずサイドからドリブルでペナルティエリアに侵入した際、(ドリブル)ボールがゴールに向かっていればGKはシュートの可能性を感じてボールに注視してしまう。
しかし、その際、FWがクロスに備えてPKスポットに向かってスプリントしている。GKはドリブラーが足元からボールが離れる瞬間、適時ペナルティエリアの中を観る(認知)する必要があった。
その情報があるだけで「中に合わせてくるかもしれない」と予測ができる。それによって味方DFに声を掛けることや、パスに備えてポジショニングをどこに立つべきかイメージができる。いざパスが放たれると、遅れを取らないようすステップを踏み(サイドステップorクロスステップ)相手が蹴る瞬間には構えを完了させる(基本姿勢)。
そしていざ放たれたシュートに対して、手を出すタイミング、手の出し方、手の形、力の入れ方は適正だったかどうかでプレーの質が決まってくるのだ。
ここまで話してお分かりになったと思うが、GKが非常に細かく繊細な技術、判断が求められるのだ。
でも指導者からすれば「そんなとこまで見切れないし、教えられないよ」
そう感じることだと思う。実はその通りでそこまで求めるのは私も酷であると思う。
では、どのようにGKと関わればいいのか。私なりに重要なキーワードとともにアドバイスをしていきたいと思う。
---------ここから先は有料コンテンツです---------